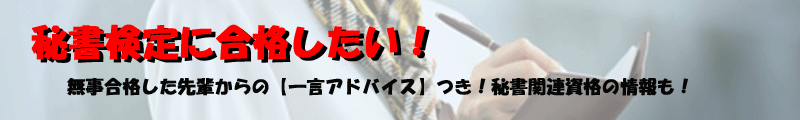秘書の仕事内容定型業務…日常的に行うもの・上司の身のまわりの世話 ・来客の接遇 ・スケジュールの管理 ・出張の際のスケジュール管理 ・会議、会合、冠婚葬祭の手伝い ・部屋の管理 ・その他 非定型業務…突発的に生じるもの・急病 秘書としての職務の限界はここまでという線引きがはっきりしないため、その境界線がかなり複雑になります。何が越権行為や独断専行になるのか、自分自身で理解し身につけましょう。 秘書の所属形態機能による分類・直接補佐型 ・間接型 所属形態による分類・秘書課に属する秘書 ・秘書検定では「間接型秘書」をしっかり覚えておきましょう。 秘書の機能と役割企業内における上司と秘書の位置ライン機能とスタッフ機能 上司と秘書の機能と役割の違い・上司:ライン機能に属する 秘書の機能と役割・秘書の機能:上司を補佐すること 応用上司の代行業務・当然すべき代行業務 ・代行してはいけない業務 秘書から上司への進言・秘書から上司へ進言してもよい項目 ・補佐役としての助言者 ・言葉遣いや態度に十分注意する 仕事が競合したときの対処・仕事が競合したとき ・注意する点 日常業務の範囲内では自己の判断で優先順位を決めることが可能ですが、その範囲を越えるものは必ず上司に相談します。 ・一人で処理できない場合 上司のスケジュール調整・スケジュール変更、調整依頼があったとき ・スケジュール変更、調整を依頼するとき ・変更、調整が決まったら 訪問者への断り方ここでの訪問者とは、取引先の相手や上司の友人を指します。今後の取引に悪影響を及ぼすことなく上手に断らなくてはなりません。 ・注意点 ・突発的事態における的確な判断力や新任上司への接し方、後輩秘書の指導など能力を発揮する場は数多くあります。 一言アドバイス自分の立場をわきまえ、的確に補佐できるようにしましょう。公私の区別をつけ、社内外での言動には注意すべきと思います。 |
職務知識(秘書検定に合格したい!)
秘書の仕事
■秘書の役割
■秘書のタイプ
■秘書になるメリット
■秘書の業務
■環境・スケジュール管理
■情報と応対
■社内外重要業務
■機密保持
■就職活動
秘書検定の概要とポイント
■秘書技能検定試験とは
■秘書検定試験科目
■合格まで
■秘書技能検定について
■出題領域と審査基準
■領域を理解する
■合格のポイント
秘書検定科目別分析
■秘書の資質
■職務知識
■一般知識
■マナー・接遇
■技能
秘書検定合格術
■秘書検定合格について
■基本書
■問題集
■ダブル受験の勧め
■勉強方法
■合格方法
■通学校の特色
■合格スケジュール
■学習方法
秘書に関連する資格
■秘書士
■国際秘書検定
■英語検定
■日本語文書処理技能検定
■秘書の資格
■秘書検定の色々
■文書処理・パソコン関連検定
■専門分野・検定
■英語スキルアップ検定
■マナー検定
■日本語と文字
求められる秘書像
インフォメーション
■ TOP(トップページ)■ お問い合わせ