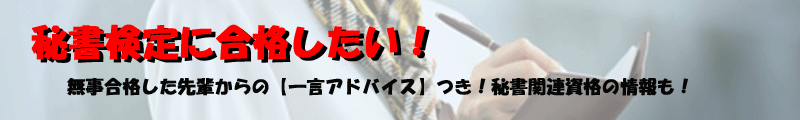経営
(会社のピラミッド型組織)
・トップマネジメント:常務以上(常務、専務、社長、会長)で構成される企業の最高経営者層、企業経営に関して最重要項目について決定します。
・ミドルマネジメント:トップマネジメントの指示・命令の下に企業の業務を担当する中間管理層。
・ロアマネジメント:最も低い管理者層で中間管理層の指揮、命令の下で業務を担当します。
(P・D・Sサイクル)
企業経営を行う根本的要素は3つあります。
(Plan)まず計画を立て熟考し、
(Do)次に計画を実施・行動します。
(See)最後に実施した結果を検討・反省します。
(マーケティング)
商品が生産者から消費者の手にわたるまでの一切の活動のことをいいます。
市場調査、製品計画、価格政策、販売促進、流通政策、アフターサービスの一連の活動のことをいい、一部部のみの場合はマーケティングとは言いません。
(経済四団体)
・経済団体連合会:経団連
・日本経営者団体連盟:日経連
・日本商工会議所:日商
・経済同友会:同友会
会社の仕組み
(所有と経営の分離)
組織が大きくなるにつれて、経営には経営手腕の優れた専門家が必要となります。ここに所有と経営の分離現象が生じてきます。
会社の「所有」は株主にあり、会社の「経営」は取締役会にあります。
(株主・取締役会・代表取締役・監査役)
株主:会社の所有者のことで、10人の株主がいれば10人で共同して所有していることを意味します。
取締役会:取締役で構成される会議体をいいます。
取締役とは会社役員のことで、株主総会で3名以上選出されます。
代表取締役:会社の代表者のことで、俗称では社長といわれています。
監査役:代表取締役や取締役の業務執行について監査し、同時に、会計監査についても監査します。
(会社の種類)
・株式会社:商法によって設立された会社で、物的会社であり、会社の財産、株主の個人財産は、明確に分離され、一人でも株主となり、設立できます。
現在は、中小企業にも多く利用され、社員の責任は有限責任です。
・有限会社:有限会社法により設立された会社で、中小企業向きです。
社員は50人までで、有限責任です。
・合名会社:商法により設立された会社で、家族企業、小規模企業が適切です。
社員が会社の債務を無限に責任を負います。
・合資会社:商法により設立された会社で、無限責任社員(執行役員)と有限責任社員(一般社員)の二元組織から成り立っています。
手形・小切手
(約束手形)
振出人が一定の期日に一定金額を名宛人又はその指図人に支払うことを約束した証券をいいます。
(手形割引)
手形の支払期日以前に金融機関などが利子相当額を差し引いて、その手形を買い取ることをいいます。
(裏書)
手形・小切手・証券などを他人に譲渡する時、所持人がその証券の裏に譲渡した旨の署名をすることをいいます。
(小切手)
振出人が受取人への支払を支払人に委託した証券をいいます。(支払委託証券)
(先日付小切手)
実際の振出日より先の日付を振出日として記載した小切手のことをいいます。
支払人である支払銀行の振出人の当座預金に残高がないと、その小切手は不渡りとなるため、当座預金に入金できそうな日付を振出日とします。
(横線小切手)
表面に2本の平行線を引いた小切手のことで、一般線引小切手(支払人が銀行・自分の取引先に対してのみ支払う小切手)と特定線引小切手(二本線の中に具体的な銀行名が入っている小切手で、支払銀行は指定された特定銀行に対してのみしか支払うことができません。)があります。
法律の一般知識
・割印
書類が2枚以上にわたる場合、正当に作成された文書であることを示すために押される印をいいます。
・訂正印
文字の字句を訂正する時、権限のある者が訂正したことを明らかにするために、訂正箇所に押す印をいいます。
・捨印
将来文書の字句を訂正する必要のある時に備えて、あらかじめ文書の欄外に押しておく印をいいます。
・消印
切手・収入印紙の再利防止のため、印紙と台紙にまたがって押印することをいいます。
・収入印紙
税金や手数料の納付に際して利用する国が発行する証票のこと。
郵便局・切手類取り扱い所で買うことができます。
収入印紙が必要な書類は、契約書、領収証、必要のない書類は、委任状、請求書です。
・内容証明郵便
郵便物の内容が、どのようなものであるかを証明するためのもので、郵便法により書留で送ります。
同じ書面を3通作成、1通目は差出人、2通目は郵便局、3通目を受取人に発送します。
・契約書
契約は口約束でも成立しますが、後日、紛争が生じた時に内容確認する為のものです。
財務
・財務諸表
株主はじめ利害関係人に報告されるために作られるいろいろな計算書類のことをいいます。
・貸借対照表(B/S)
バランスシートとも言われ、決算期の資産・負債・資本の内容を表したものです。
・損益分岐点
売上高と総費用が等しくなる点をいいます。
売上高が総費用を超えると利益発生、総費用が売上高を超えると損失発生になります。
・減価償却
建物・機械・設備などの土地以外の固定資産は一定の耐用年数があり、いつまでも使用できるものではありません。
買った年に全部計上するのではなく、使用した期間の費用として配分していきます。
・市場占有率
各企業の特定の業界において、その企業の販売額や販売量の割合をいいます。
・連結決算
親会社と子会社などを別々にして決算を出すのではなく、一括し、全体としてまとめて経営内容を明らかにする決算のことをいいます。
・経営の多角化
企業の危機分散を目的とし、本来の経営活動以外の分野にまで業務範囲を拡大していくこと。
・直接税
税金を納入義務者が負担し、直接納める税金をいいます。
所得税・法人税・相続税がその例です。
・間接税
税金を負担するものが自分自身で直接納めない税金のことをいいます。
用語
・リストラクチャリング
企業再構築といわれ、一般的にはリストラという、解雇と理解されています。
リストラ=解雇ではなく、部署の廃止、人員移動も含まれます。
・PL法
製造物である欠陥商品によって人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、その商品を製造した企業に直接責任を追及することができる法律。
・フリーエージェント制
プロ野球の選手で、本人の自由意思により、所属球団以外の球団とも契約を結ぶことのできる制度のことをいいます。
一言アドバイス
ここで出てくる用語など、秘書検定に出題されることが多いです。用語、意味など、しっかりマスターしておきましょう。
|